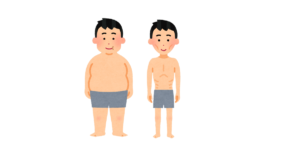おくすり千一夜 第九十二話 急性脳症は薬害では?
三月始め(2000年)、読売新聞の医療ルネッサンス欄に「インフルエンザ・子供と脳症」と題して5回にわたって特集が掲載されました。内容を断片的に拾ってみますと、
*「昨年1~3月に全国で217人が発症、61人が死亡。患者の8割は5歳以下の乳幼児」
*「インフルエンザと診断され、解熱剤と抗生物質を医師から渡された」
*「インフルエンザによる脳症が問題になっているのは日本だけ。解熱効果の高いメフェナム酸やジクロフェナックなど、強力な解熱剤を使っているのも日本だけ」
* 厚生省研究班によると「脳症患者の65%は解熱剤を使用。そのうちメフェナム酸(ポンタール)を使った患者の死亡率は67%、ジクロフェナックナトリウム(ボルタレン)では52%。解熱剤を使わなかった患者の死亡率は25%。これを統計処理すると、死亡の危険度は、使わなかった場合に比べ、それぞれ4.6倍と3.1倍に上昇していた」。このデータだけで解熱剤が犯人とは言い切れないという意見も添えられていた。
*「脳症を起こすウイルスは、インフルエンザ以外にも多い。突発性発疹、風疹、麻疹、手足口病や、普通の風邪の原因であるアデノウイルスのこともある。」
*「現在、インフルエンザ脳症の発症のメカニズムは不明、ウイルスを押さえるために体が出す物質(サイトカイン類)が過剰に出て脳を壊すのでは」という見方が有力。
* 薬の評価を行なう医療ビジランス(監視)センターの浜六郎氏は「熱で脳が侵される心配はない。これら2剤だけでなく非ステロイド系抗炎症剤も解熱剤としての使用を禁止すべき」と主張。
ざっと以上です。インフルエンザと脳症について国内外で、これまでどのような経緯を辿ったのか再度お話しましょう。
*1963年、今から37年前オーストラリアの病理学者Reye氏らが原因不明の小児の疾患に関する論文を科学誌「Lancet」に発表。
*1980年、4つの疫学調査がライ症候群にサリチル酸の関与を指摘。
*1982年、米国保健省長官は「アスピリン系の解熱剤を水痘やインフルエンザに使用すると、ライ症候群になりやすい」との警告文を公表。
*同年、米国小児科学会は、「臨床的、疫学的証拠にもとずき、水痘の小児またはインフルエンザが疑われる小児に対しては、普通の場合アスピリンを処方すべきでない」との勧告文を学会誌に掲載。
*1982年、厚生省も調査開始。内容は未公開。単に「我国の調査では本症とアスピリンの関連性は立証出来ず、本症の原因は不明である」とのみ報道。
*1983年、アメリカではライ症の発生は調査始まって以来の最小値となる。
*1984年、保健省がアスピリンを服用しないようキャンペーンを実施。
*1985年、アメリカでは発症者数が年間600~1200人から90人台にまで激減。
*1998年11月、日本のThe Informed Prescriberは「解熱剤は基本的には不要」との解説を掲載。
*1998年末、厚生省は「サリチル酸製剤の15才未満の小児の服用はこれを認めない」旨やっと通告。
最近の我が国のインフルエンザと脳症に関する報道には「ライ症候群」という言葉がありません。多分、ライ症候群はアスピリン若しくはその誘導体を使用したことによる脳症を意味するように思われます。
我が国の医療の場ではアスピリンが駄目なら、他に強力な薬剤がいくらでもあるさという医療者側の考え方と、速やかな治療効果の発現を強く期待する被医療者側の風潮とが悲劇を助長しているように思えてなりません。
何故アメリカやヨーロッパでアスピリン脳症が多発したのでしょう。それは幼児にはアスピリン以外に解熱剤の投与は認められていなかったからです。アセトアミノフェンが使われようになったのはごく最近です。
我が国では一昨年アスピリン使用禁止の通達がでるまで、あらゆる解熱鎮痛剤の投与が認められておりました。外国では症例の無くなったインフルエンザ脳症が、いま猛威をふるっている最大の要因は、アスピリンより更に強力な非ステロイド系の解熱消炎鎮痛剤が坐剤の形で小児に相変わらず使われているからなのです。これは正しく薬害です。
2022年の現状
小児への解熱剤としてのNSAIDsは、国際的にはアセトアミノフェンとイブプロフェンが推奨されていますが、我が国で推奨されているのは、現在アセトアミノフェンのみです。
安全性が高いと認識されているアセトアミノフェンですが、催奇形性の指摘はないものの、妊娠後期の使用で動脈管閉鎖による胎児死亡を促すことがあり、また、羊水過少症の注意も加わって、妊娠全期間で注意喚起されています。
よく効く薬には副作用がつきものであることを、忘れてはなりません。(小鬼)